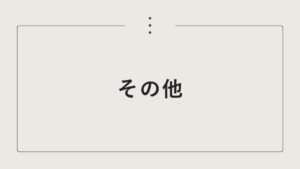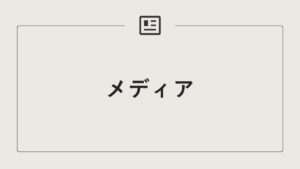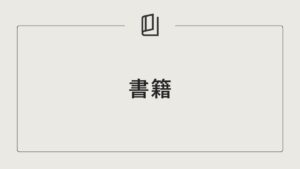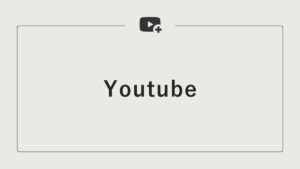西岸地区はどこにある?
「パレスチナ」という地名は、歴史的にはシリアの南部一帯を指します。
この地域は、16世紀以降はオスマン帝国の一部として、イスラム教徒・ユダヤ教徒・キリスト教徒が共存してきました。
しかし、19世紀末、民族主義の台頭や欧米列強の植民地主義の拡大に伴い、この地に長く続く危機が訪れます。
1918年、パレスチナは第一次世界大戦で敗れたオスマン帝国から、イギリスの統治下に入りました。
現在、イスラエルとパレスチナの領土がある、西は地中海・東はヨルダン川と死海に挟まれた細長い地域は、この「イギリス委任統治領パレスチナ(British Mandate for Palestine)」とほぼ一致します。
現代の地図を見てみると、中央にイスラエルがあり、その左右に2つの「パレスチナ自治区」が隣接しています。
左側の地中海に面する小さな地域がガザ地区。そして右側にあるのがエルサレムと、その東に位置するヨルダン川西岸地区(West Bank)です。

(画像:WorldAtlas “Maps of Palestine”より)
本記事ではこの西岸地区について解説します。
📍ポイント解説
イスラエル建国に伴う1948年の第一次中東戦争後、パレスチナのガザ地区はエジプト領、西岸地区はヨルダン領に組み込まれました。
その後、1967年の第三次中東戦争の結果、ガザ地区と西岸地区もイスラエルに占領されました。
パレスチナは現在「国家」としての独立が認められておらず※1、ガザ地区と東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区は、日本では「パレスチナ自治区」、国際的には「パレスチナ被占領地(Occupied Palestinian Territory:OPT)」と呼ばれています。
※詳しくは「パレスチナ“自治区”」の解説へ
西岸地区においては、2007年以降完全封鎖されているガザ地区とは異なる形での抑圧が続いています。
西岸地区の多くはイスラエルの軍事占領下にあり、パレスチナ自治政府の統治は限定的です。その上、「検問所」、「入植」、「分離壁」に象徴される日常的な暴力が横行しています。
2023年10月7日以降、ガザ地区におけるイスラエル軍による過去最悪の攻撃が国際的な注目と批判を集めていますが、その影で西岸地区でも暴力がエスカレートしています。
アムネスティ・インターナショナルによれば、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区ではイスラエル軍や入植者による襲撃が激しくなり、2023年10月以降子ども142人を含むパレスチナ人622人以上が殺害されています。(2024年9月時点)
✅ステップアップ解説
「穴ぼこ」だらけの西岸地区
ヨルダン川西岸地区には、三重県とほぼ同じ広さに約325万人のパレスチナ人が住んでいます。この地域は、11の行政区と19の難民キャンプが存在する一方で、以下のように3つのエリアに分けられています。
| 行政 | 治安 | 面積 | |
| A地区 | パレスチナ自治政府 | パレスチナ自治政府 | 18% |
| B地区 | パレスチナ自治政府 | イスラエル軍 | 22% |
| C地区 | イスラエル軍 | イスラエル軍 | 60% |
西岸地区全体がパレスチナ自治政府の統治下にあるわけではなく、パレスチナ自治政府が行政・治安を行うA地区は、面積の18%に過ぎません。
そして、最大面積のC地区はイスラエルが行政と治安の両方を管理しており、パレスチナ人の活動が厳しく制限されています。
西岸地区には現在、200以上もの違法なイスラエル人入植地(パレスチナ人の土地を強制的に奪い、イスラエル人が居住している土地)がありますが、その大部分がこのC地区に存在し、40万人以上の入植者が住んでいると言われています。
また、エルサレムの南に位置する都市・ヘブロンには「H2地域」と呼ばれる特別なエリアが存在し、こちらもイスラエル軍が治安・行政を管理しています。
※参考動画:
H2エリアでの取材の動画ルポ - 「暴力は日常、それが占領」 入植進むパレスチナヨルダン川西岸ヘブロン 占領下の土産物店で働く人々の声とは(8bit news)」https://www.youtube.com/watch?v=_O3AJ2wthJE
占領国が被占領地に入植地を建設することは国際法違反であるにもかかわらず、イスラエルは入植を拡大し続けています。
このような入植に加え、西岸地区を侵食する「分離壁」、パレスチナ人の移動の自由を妨げる140ヶ所もの「検問所」、違法な家宅侵入や刑務所での拘束(未成年を含む)など、パレスチナ人に対する日常的な暴力が横行しています。
自治政府の汚職問題
ファタハが主導する西岸地区のパレスチナ自治政府は、イスラエルの暴力に対処することができていない上に、イスラエルの占領に抗議する住民を取り締まるなど、イスラエルの「下請け」役になっており、イスラエルの占領政策の一部に組み込まれていると批判されています。
さらに、パレスチナに対する国際援助を着服する汚職が横行するなど、その腐敗ぶりが問題視されているのが現状です。
🔎深掘り
西岸地区では、ガザのような大規模な空爆は少ないものの、イスラエルによる「見えにくい暴力」が日常的に行われています。ここでは、その代表的な事例を3つ紹介します。
1. 検問所
ヨルダン川西岸地区には、イスラエル軍による検問所が多数設置されており、パレスチナ人の移動を厳しく制限しています。
2023年、OCHA(国際連合人道問題調整事務所)は、西岸と東エルサレムにはパレスチナ人の移動を規制するために、合計645ヶ所(うち49ヶ所が常駐の検問所、139ヶ所が非常駐の検問所)もの物理的な障害が設置されていることを報告しています。
これらの検問所では、パレスチナ人は身分証明書の提示や荷物の検査が強制されます。公式な理由としては「テロ対策」とされていますが、実際には基準が不明確で、不当に通過が許可されないことが日常的に起きています。これにより、通勤や通学、さらには病院への緊急搬送も妨げられ、患者の容体が悪化したり死亡するケースも少なくありません。
2. 入植地の拡大
イスラエル政府は、前述のC地区を中心に違法な入植地の建設を続けてきました。入植地の建設は国際法に反しているにもかかわらず、多くのパレスチナ人が強制的に立ち退かされています。パレスチナ人の住む家屋や農地は次々に取り壊され、その土地にイスラエル人が住む新たな入植地が建てられ、そこにイスラエル人の入植者たちを住まわせることで、入植地を拡大し続けています。
さらに、入植地同士を結ぶ入植者専用道路が建設されており、これがパレスチナ人の移動をさらに制限しています。こうした入植活動は、イスラエルがパレスチナの土地を自国の領土として既成事実化するための政策と考えられています。
2024年7月19日には、国際司法裁判所(ICJ)が「イスラエルによるパレスチナ自治区の占領および入植活動は国際法に違反しており、可能な限り早期に明け渡すべき」という勧告的意見を出しましたが、イスラエルはこれに反発しています。
3. 分離壁の建設
2002年以降、イスラエル政府は「テロリストの侵入を防ぐ」という名目で、イスラエルと西岸地区を隔てる分離壁を建設しています。
場所によっては8mの高さにもなるコンクリートの壁が築かれ、完成すると総延長710キロメートルもの長さになる分離壁(アパルトヘイト・ウォール)は、1949年の停戦ライン(グリーンライン)を超え、西岸地区内部に大きく食い込む形で設置されています。
分離壁や入植地専用道路にぐるりと囲まれた結果、周囲から分断状態になってしまっている村もあります。
分離壁は、パレスチナ人の生活を物理的にも精神的にも分断する象徴となっています。
10月7日以降の西岸地区の状況
2023年10月7日以前から、西岸地区ではイスラエルによる強制移住や家屋の破壊、逮捕、違法な拘束などが日常的に行われていました。
このような暴力は子どもたちに対しても容赦なく行われており、年間700人、平均して1日2人の子どもたちがイスラエル軍に逮捕されていると言われています。※2
10月7日以降、状況はさらに悪化し、次のような被害が報告されています。
- 少なくとも719人のパレスチナ人が殺害された。
- その中には、160人以上の子どもが含まれている。
- 5700人以上のパレスチナ人が負傷。
- ヨルダン川西岸地区と東エルサレムで1330の建造物が破壊された。
- 過去20年間で最大の規模23.7㎢のパレスチナの土地が奪われた
- 70万人以上のユダヤ人入植者がヨルダン川西岸地区と東エルサレムの300以上の違法な入植地に住んでいる。
- 9900人以上のパレスチナ人がイスラエルの拘束下にある(2024年9月時点。ガザも含む)
(参考 @palestinejpn ファクトシート https://palestinejpn.com/files/1-year-of-genocide.pdf より)
特に、ジェニン難民キャンプでは、イスラエル軍による装甲車や戦闘機、ドローンを使った大規模な襲撃が行われ、多くの住民が避難を余儀なくされました。このような激しい攻撃が続いていることから、ジェニンは「リトル・ガザ」とも呼ばれています。
サラ・ロイ氏(ナチス・ドイツのホロコースト(ユダヤ人大虐殺)を生き残った両親を持つ政治経済学者。『ホロコーストからガザへ』の著者)は、「もしガザ地区が陥落すれば、次は西岸地区の番だ」と警告しています。
彼女は、ガザでのジェノサイドが放置されると、次に西岸地区が同様の弾圧や攻撃を受ける可能性が高いと指摘し、ガザへの国際的無関心が続けば、西岸地区でもイスラエルによる「段階的な併合」が進む恐れがあると強調しています。そのため、西岸地区にもガザと同様の注目と支援が必要だと警鐘を鳴らしています。
参考文献:
ぼくの村は壁で囲まれた p17-28
パレスチナ/イスラエルのいまを知るための24章 p144-152
ガザ紛争 p61-78
パレスチナを知るための60章 p.4、P.139
ガザとは何か〜パレスチナを知るための緊急講義
ホロコーストからガザへ パレスチナの政治経済学
※1ただし、国連加盟国193カ国中138カ国がパレスチナを国家承認しており(2022年4月時点)、2012年には国連の「非加盟オブザーバー国家」として認められています。
※2 2023年、NHKが主催する教育番組・教養番組作品の国際コンテスト「日本賞」でグランプリを受賞した「Two Kids a Day(トゥー・キッズ・ア・デイ)」は、イスラエル兵に投石したとして数年間拘束されたパレスチナの少年たちにスポットを当てたドキュメンタリーです。現在、Youtubeで配信されています。公式字幕はアラビア語とヘブライ語のみですが、自動翻訳で日本語字幕をつけることができます。
コラム
〜西岸地区を訪れて感じていること〜

(写真:パレスチナ西岸地区・ナブルス旧市街の商店街)
西岸地区に足を踏み入れ、占領下での生活がどういうものかを肌で感じる機会を得ました。
検問所を通るときの厳重な検査や、あちこちで見かける軍の存在、そして分離壁や入植地の広がりは、占領が日常の隅々にまで深く入り込んでいることを痛感させます。厳しい制約が課される中での生活は決して豊かとはいえませんが、それでもパレスチナの人々は明るく親切で、前向きに力強く生きている姿が印象的でした。
特に心に残っているのは、旧市街の風情ある街並みや活気ある商店街で出会った人々とのやりとりです。どこに行っても温かく迎え入れてくれ、お茶をすすめてくれたり、パレスチナの歴史や文化について丁寧に話してくれたりしました。食べ物を買ったりレストランで食事をした際には、代金を受け取るのを断られることもあり、「遠くから来てくれてありがとう」と逆に感謝の言葉を添えられることもありました。困難な状況の中にありながら、見知らぬ来訪者に温かい気持ちを向けるそのホスピタリティには、深く心を打たれました。
「紛争地」という表面的なイメージとは違い、そこには、日々を懸命に生きる人々の“ごく当たり前の日常”がありました。そして、その日常の風景の中に、パレスチナの長い歴史とその地に深く根づいた文化が息づいていました。繊細な刺繍が施された衣装、美しい手作りの陶器、地元産のオリーブやそこから作られた製品、香り高いスパイスが並ぶ市場、伝統料理や甘くてとびきり美味しいスイーツ。どれも人々が苦難の中で守り続けてきた、この土地の豊かな文化とアイデンティティを感じさせます。
もしも占領がなければ、パレスチナは歴史と文化、そして人々の心温まるホスピタリティで、世界中の人を魅了する場所になるでしょう。ここに暮らす人々が何世代にもわたって守り続けてきた生活や、文化や歴史が、どうかこれからも失われることなく未来へと受け継がれてほしいと心から願います。ガザでは多くのものが破壊されてしまいましたが、西岸地区にはまだ守られている風景や文化が残っています。私たちにできることは小さいかもしれませんが、パレスチナが脈々と築き上げてきた歴史や文化がこれ以上壊されることがないように、パレスチナの人々が自由に安全で暮らせる日が来るように、できることを模索していきたいと思います。
<Olive Journal運営 塚田有希>

(写真:パレスチナ西岸地区・ナブルス旧市街にある時計塔。)
※サムネイル写真:パレスチナ西岸地区・ヘブロンにて撮影したもの